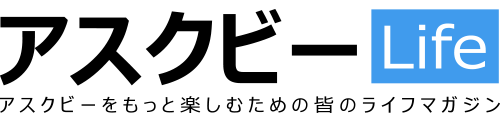【事務で手に職をつける!】経理や総務のスキルはオンライン講座や勉強会を活用しよう
未経験からでも始めやすい総務や経理の仕事は、作業の仕方さえ覚えてしまえばある程度こなせるようになります。
一方で、言われた通りやっているだけでは、大してスキルも身につきません。
バックオフィス担当として成長していくためにも、資格や検定の取得を目指してみましょう。
とは言っても、資格や検定は総務向けのもの、経理向けのものなどいくつか種類があるので、自分が伸ばしたいスキルや携わっている業務内容を選んで学習することをおすすめします。
本記事では、総務と経理の基本スキルと、それぞれどこで学ぶことができるのかについて詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
1. 総務や経理の仕事にスキルはあった方がいい?
もしあなたが総務や経理に関する仕事をしていて、将来的にスキルアップや転職なども考えているようであれば、積極的に専門スキルを獲得すべきです。
自分の業務が何にどう生かされているのか分かるようになると、自然と仕事の幅も広がります。
しかも転職サイトでは「簿記資格者優遇・歓迎」といった募集の仕方をしているところも多いです。
つまり、総務や経理のスキルを身に付けることは、今の仕事にも将来の自分にとってもプラスに働くといえます。
その場しのぎで何となく仕事をするよりも、日々の業務と勉強を組み合わせてスキルを確実に獲得していきましょう。
2. 総務の仕事に必要な基本スキル

書類作成はもちろん、消耗品の購入や従業員の健康管理など、業務の幅は多岐に渡るため、覚えなければいけないことも必然的に多いです。
だからこそ検定を目標に学習を積んでいくことで、実際の業務をスムーズに進めることができます。
2-1. ビジネスキャリア検定
通称「ビジキャリ」と呼ばれる「ビジネスキャリア検定」とは、人事や労務、企業法務などの試験区分から自分の業務にあったものを選び、知識やスキルを評価する検定です。
総務としてスキルを深めるなら「人事・人材開発」もしくは「労務管理」で受験するのが良いでしょう。
大学生程度のBASICから、実務経験10年以上を対象とする1級まで全部で4つの等級があり、総務担当であれば「実務経験3年程度」の3級から受けてみるのがおすすめです。
2-2. 衛生管理者
従業員が50人以上いる会社は、健康管理などを目的に「衛生管理者」を置くことが法律で定められています。
衛生管理者は「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」の2種類があり、いずれも約4割ほどの合格率ですが、一度取得すれば更新もないので、受験できるタイミングがあればぜひ取っておきたい資格です。
両者の違いは「有害業務に係るもの」が試験内容に入っているかどうかで、有害なガスや粉が発生するような労働環境においては、第一種衛生管理者がこれに該当します。
衛生管理者試験の受験資格はあり、その中からいくつか抜粋すると次の通りです。
- 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
(引用:公益財団法人安全衛星技術試験協会)
基本的には実務で取り扱っている必要があるため、現時点で必要がないとしても、いずれ受験することを頭の片隅に置いておきたいですね。
なお、試験は全国各地域の衛生技術センターで行われていますが、地域によっては県外まで行くこともあるので、最寄りのセンターや受験日程を確認しておきましょう。
2-3. メンタルヘルスマネジメント検定
仕事をする上で、職場の人間関係や業務内容に対するストレスや悩みはつきません。
特に近年は心の不調を理由とした休職や離職も多く、企業にとって労働者の心のケアを行ったり、必要な制度を設置したりすることが求められています。
これを「メンタルヘルス」といい、平成30年度に厚生労働省が公表した「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果によると、約6割の事業所がすでにメンタルヘルス対策に取り組んでいるそうです。
従業員の健康管理等については総務が担当になるケースが多く、メンタルヘルスマネジメント検定の取得を推奨されている職場もあります。
メンタルヘルスマネジメント検定とは、業務で必要になるであろうメンタルヘルスに関する知識や、対応方法を習得することを目指した資格です。
コースは目的や対象に応じてⅠ種・Ⅱ種・Ⅲ種の3種類があり、受験資格は特にないため業務内容や力量に応じて受験することができます。
Ⅲ種はセルフケアに重きを置いたコースなので、業務での活用を目指すならまずはⅡ種の取得から目指してみましょう。
3. 経理の仕事に必要な基本スキル

では次に、経理の仕事に関係する2つのスキルについて確認していきます。
3-1. 日商簿記
経理をするならぜひ持っておきたいのが簿記資格です。 経理は企業の経営活動を記録・計算し、整理することで財政状況が見えるようになります。
日商簿記では、財務諸表の見方や分析の仕方に関する出題もあるため、検定に向けて学習を重ねることで業務で十分に力を発揮できるようになるはずです。
まずは3級の取得から始め、少なくとも2級以上を持っていれば転職の時にも有利に働きます。
企業規模にもよりますが、経理総務がまとめられている部署もあり、業務を遂行する上で必要になる場面は多いので、とりあえず何かしら勉強がしたいという人は、日商簿記の資格取得を目指すことをおすすめします。
3-2. FASS(経理・財務スキル検定)
「FASS」とは、合否ではなくレベルで受験者の経理・財務スキルをAからEの5段階で評価する検定です。
経済産業省が、経理や財務業務をする過程で、どのような知識や行動が必要になるのかを細かく分析した指標に「経理・財務サービス・スキルスタンダード」があります。
FASSは、この指標にアメリカのテスト理論を組み合わせて作られたものです。 知識というよりも実務対応を重視した内容で、四択形式で出題されます。
FASSを受験することで客観的にスキルレベルが分かりますし、合否で評価されないので気持ちもめげません。
どの分野に対して自分の知識を深めるべきなのかを考えるきっかけにもなるので、力試しとして受験してみるのもいいかもしれませんね。
4. おすすめのオンライン講座

同僚や先輩から業務を教わるとしても、体系的に全体を見渡せるような教え方はしてもらえません。
確実にスキルを習得するなら、スキマ時間を使ってオンライン講座を受けてみましょう。
総務や経理の業務に生かせる講座をいくつか紹介します。
4-1. 日経ビジネススクール
日本経済新聞社が運営している「日経ビジネススクール」は、企業の経営者から若手まで幅広く利用できるスクールです。
各講座によって受講費用は変わりますが、メンタルヘルスに関する講座は約15,000円、社会保険に関する講座は約40,000円ほどで設定されています。
数々の実績や経歴をもつ講師がeラーニング教材を担当しており、質の高さではピカイチです。
なお、日経ビジネススクールは学習期間があらかじめ決められているので、受講したい時期に合わせて期日までに申し込みを済ませておくようにしましょう。
4-2. Udemy
Udemy(ユーデミー)は、ビジネスから自己啓発系、趣味を動画レッスンで幅広く学ぶことのできるオンライン講座です。 講座ごとに5,000円から3万円程度の受講料を支払うことで、いつでもどこでも学習可能です。
YouTubeで学ぶのもいいですが、やはりお金を払って学べる講座は内容も本格的で、ランキング上位の講座は受講者からの評価が高いのもうなずけます。
講座は基礎をくまなく学ぶことのできるパック型、「会計&簿記」のカテゴリから、簿記や財務会計、財務表、原価計算などピンポイント型まであるので、自分の意欲や予算にあったから始めてみてください。
4-3. ユーキャン(通信講座)
CMでもおなじみのユーキャンは、数ある講座から自分の受けたいものを選び、届いた通信教材などを使って学習していくスタイルです。
試験日までのスケジュールを示してくれますし、資格との相性を診断してくれるようなユニークなツールがあるので、勉強を始める後押しをしてもらえます。
とりあえず本屋でテキストを買ったものの、思ったような内容ではなかったり、動画だといまいち頭に入ってこなくて勉強が進まない人には特におすすめです。
総務や人事、経理事務におすすめの資格の上位には、先ほど紹介した衛生管理者やメンタルヘルスマネジメント検定、簿記などもランクインしています。
ちなみに料金は、簿記講座が39,600円、メンタルヘルスマネジメント検定講座は29,800円です。
もちろん、総務や経理以外の資格もたくさんあるので、面白そうと思った講座があれば受講してみると良いでしょう。
5. まとめ

総務や経理は会社で教えられるやり方さえ分かっておけば何となくでも仕事はできますが、それではなかなかスキルは身につきません。
先輩や上司のように手広く業務を扱えるようになりたい人は、毎日少しずつでも学習してスキルや資格を取得していくことが、現状を抜け出す一歩となります。
企業によっては、受験費や資格手当を出してくれたり、eラーニング教材を無料で受講できたりするような福利厚生が設けられているところもあるので、うまく利用しながらスキルアップを目指していきましょう。