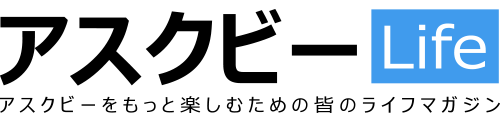独学で介護福祉関連の資格は取得できる?おすすめ資格・勉強法・動画を紹介
高齢化社会に伴い、介護福祉関連の資格を取得して従事しようと考える人もいるかもしれません。介護福祉の仕事は、特に資格がなくても問題ありません。
しかし、取得しておけば給与アップなどのメリットがあります。
そのような介護福祉関連の資格ですが、さまざまな理由から独学で取得したいと考える人もいるでしょう。
そこで独学で取得可能な資格や勉強法について解説します。
あわせて独学に便利なおすすめ動画も紹介するので、参考にしてください。
1. 独学で取得可能な介護福祉関連の資格3選

介護福祉関連の資格は種類が多く、なかには厳しい受験資格が設けられているものもあります。
そのような条件付きの資格の場合、独学での取得は難しいかもしれません。
ここでは、独学でも取得可能な介護福祉関連の資格を紹介します。
まずはこれから紹介する資格を取得し、段階的にレベルアップしていきましょう。
1-1. ケアクラーク
受験資格: 特になし
試験日程: 1月、5月、9月(年3回)
実施方法: 在宅
試験形式: 学科:択一式/実技:報酬請求事務、給付費明細書作成
試験時間: 学科:50分/実技:60分
受験料: 6,900円(税込)
合格基準: 学科・実技それぞれの得点率が70%以上
参考:試験概要|ケアクラーク技能認定試験(ケアクラーク®)|日本医療教育財団
ケアクラークは、介護福祉関連の仕事に必要な知識・技能のレベルを評価・認定することを目的とした資格です。
試験の内容・対象は介護サービスにおける日常的な事務処理だけにとどまらず、報酬請求事務も含まれています。
介護福祉に関する幅広い知識とスキルが身につく資格といえるでしょう。
資格試験に合格すれば「ケアクラーク」の称号が付与され、勤務先によっては資格手当などがつくこともあります。
1-2. 福祉住環境コーディネーター
主催者: 東京商工会議所
受験資格: 特になし
試験日程: 年2回(公式サイトを要確認)
実施方法: 自宅・勤務先によるIBT方式・CBT方式
試験形式: 多肢選択式
試験時間: 90分
受験料: 3級:5,500円(税込)/2級:7,700円(税込)
合格基準: 3級・2級ともに100点満点中70点以上
参考:東京商工会議所検定サイト | 試験要項 | 受験案内・お申込み | 福祉住環境コーディネーター検定試験®
福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障がいのある方に住みやすい環境をアドバイスするために必要な知識・スキルを身に着けるための資格試験です。
具体的な例としては、スロープや手すりの設置場所・方法やバリアフリーの提案などを行います。
心身ともに負担のない住環境を提案することが目的です。
2024年3月時点では3級と2級までしか設けられていませんが、将来的には1級まで設けられます。
1級の試験内容や日時については公式サイトにて情報が公開されるでしょう。
興味のある方はこまめにチェックしてみてください。
1-3. ケアマネジャー
主催者: 厚生労働省
受験資格: 特定の国家資格を保有/指定業務を5年以上かつ900日以上経験
試験日程: 年1回
実施方法: 会場
試験形式: 自治体による
試験時間: 120分
受験料: 自治体による
合格基準: 分野ごとの正答率70%以上
参考:介護支援専門員(ケアマネジャー)|厚生労働省
ケアマネジャーは介護福祉関連の資格のなかでも最難関といわれている試験です。
受験資格は、指定の国家資格保有者または指定業務を一定期間経験したものと設定されています。
受験資格を得るために、通信講座や専門学校などに通う必要はありません。
たとえば指定業務を一定期間こなしながら、教材を書店などで購入して独学で必要な知識を身に着けることも可能です。
ただし、試験内容はレベルが高く、簡単に合格できる資格ではありません。
独学で取得を目指す際には、長期間にわたるモチベーション維持も重要になるでしょう。
2. 独学で介護福祉関連の資格を取得する方法

介護福祉関連の資格取得を目指す場合、さまざまな理由から独学を希望する方もいるでしょう。
資格にはさまざまなレベルがありますが、独学での取得を目指す場合、重要なポイントとして主に以下の3つがあげられます。
・テキストの読込
・過去問
・模擬試験
それぞれのポイントについて解説するので、参考にしてください。
2-1. テキストを読み込む
介護福祉関連の知識ゼロの状態で資格取得を目指す場合、最初にしなければならないことはテキストの読込です。
試験に限らず、日常的な業務のなかには専門用語が飛び交うことも多く、それらの知識がなければ仕事は困難になるでしょう。
試験でも専門用語が多く出題されるため、テキストをしっかり読み込んで多くの基礎知識をしっかり身に着ける必要があります。
テキストについては、まずは受験する資格試験に関連したテキストを1冊購入して学習しましょう。
何度も繰り返し読み込み、「わからない」「記憶があやふや」などの状態を克服することが重要です。
介護福祉関連のテキストは書店に多く並んでいます。
しかし、複数のテキストを並行して利用すると混乱を招く原因になりかねません。
まずは1冊のテキストをしっかり読み込んでください。
2-2. 過去問を解く
テキストの読込が完了したら、過去問を解いていきましょう。
過去問が掲載された問題集を購入する際は、テキストとセットになっているものを選ぶことをおすすめします。
テキストと連動した問題集のほうが、試験で重要となるポイントなどが把握しやすいからです。
また、過去問のなかには理解しにくいところも出てくるかもしれません。
その場合、問題集に付属した解答例とあわせてテキストも確認すれば、より理解度は高まるでしょう。
過去問には可能な限り多く触れてください。1冊分の過去問を解き終わったら、問題集に取り掛かりましょう。
時間をおいてから改めて最初の問題集に取り掛かるなどの工夫をすることで、知識が定着していきます。
2-3. 模擬試験で試験に慣れる
資格試験で合格するには、試験の形式などに慣れておくことも重要です。
本試験の形式は、過去問題が掲載されている問題集の掲載スタイルではありません。
テキストと問題集のみを利用して学習を進めたあと、試験での出題形式の違いに戸惑って本試験で本領が発揮できないということも考えられます。
過去問が多く掲載されている問題集を一通り解き終えたら、模擬試験も行いましょう。
問題集を購入する際に付属として模擬試験がついているものもあります。
しかし、これだけでは不十分です。
模擬試験のみが収録された問題集も多く出版されているので、これを利用してください。
その際、問題用紙と答案用紙が別になっているものを選ぶとより効果的です。
3. ケアマネ対策におすすめの動画3選
独学で介護福祉関連の資格取得を目指す人のなかには、ケアマネジャーを視野に入れている人もいるかもしれません。
ケアマネジャーは独学で取得できる介護福祉関連の資格のなかでは最難関に位置しています。
難しい試験であることは、毎年行われる試験の合格率でも確認可能です。
2024年度(第26回)合格率: 21.0%
2023年度(第25回)合格率: 19.0%
2022年度(第24回)合格率: 23.3%
2021年度(第23回)合格率: 17.7%
2020年度(第22回)合格率: 19.5%
参考:介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況等|厚生労働省
上記の一覧表には掲載していませんが、合格率が10%程度しかなかった年度もあります。
それくらいケアマネジャーの資格取得は難しいのです。
その一方で、独学でも取得可能な介護福祉関連の資格として、多くの人たちが合格を目指しており、YouTubeでは合格のための無料動画配信も多く見受けられます。
ここでは独学でケアマネジャーの資格取得を目指す方のために、おすすめの無料YouTube動画を紹介するので、参考にしてください。
3-1. 介護福祉士・ケアマネジャー試験対策ケアパンの森
介護福祉士・ケアマネジャー試験対策ケアパンの森は、介護福祉士・ケアマネジャーの試験に関する動画をUPしています。
試験では介護福祉法も含まれますが、聞きなれない言葉などが出てくるため、覚えにくいと感じる方も多いようです。
そのような方向けの覚え歌を公開しています。
そのほかにも聞き流しながら試験問題が確認できるなど、スキマ時間を活用した勉強の際に役立つ動画が満載です。
3-2. 吉川 正人エムアイシー
吉川 正人エムアイシーは、ケアマネジャー試験相談先端の専任講師を務めている吉川 正人氏が運営しているYouTubeサイトです。
専任講師を務めているだけあって、解説がわかりやすく、試験に重要なポイントを網羅しています。
初めてケアマネジャーの学習をする際に利用すると、理解度が深まるでしょう。
3-3. メダカの学校@miz
メダカの学校@mizは、福祉介護関連の知識ゼロの方のキャリアアップをサポート・応援するチャンネルです。
初めて学習する場合、わからない専門用語や制度が多く、初期段階でつまずいてしまう人も少なくありません。
そのようなリスクを減らすことを目的とした、初心者でもわかりやすい解説動画が多くアップされています。
またおすすめの対策教材の解説動画なども公開されており、スムーズなスタートダッシュができるでしょう。
4. 独学で介護福祉資格を取得したいなら反復学習が重要

独学で介護福祉関連の資格を取得する場合の、資格の種類や勉強法などについて解説しました。
資格の種類は多くありますが、いずれも介護福祉法という法律が関係しており、理解しながら知識を蓄積していくためには反復学習が欠かせません。
書店では多くの関連教材を目にするでしょう。
複数の教材を購入して並行活用するのではなく、1冊を使い込む方法で学習を進めることをおすすめします。
資格取得に近道はありません。
毎日繰り返し学習して、着実に合格への道を歩んでください。